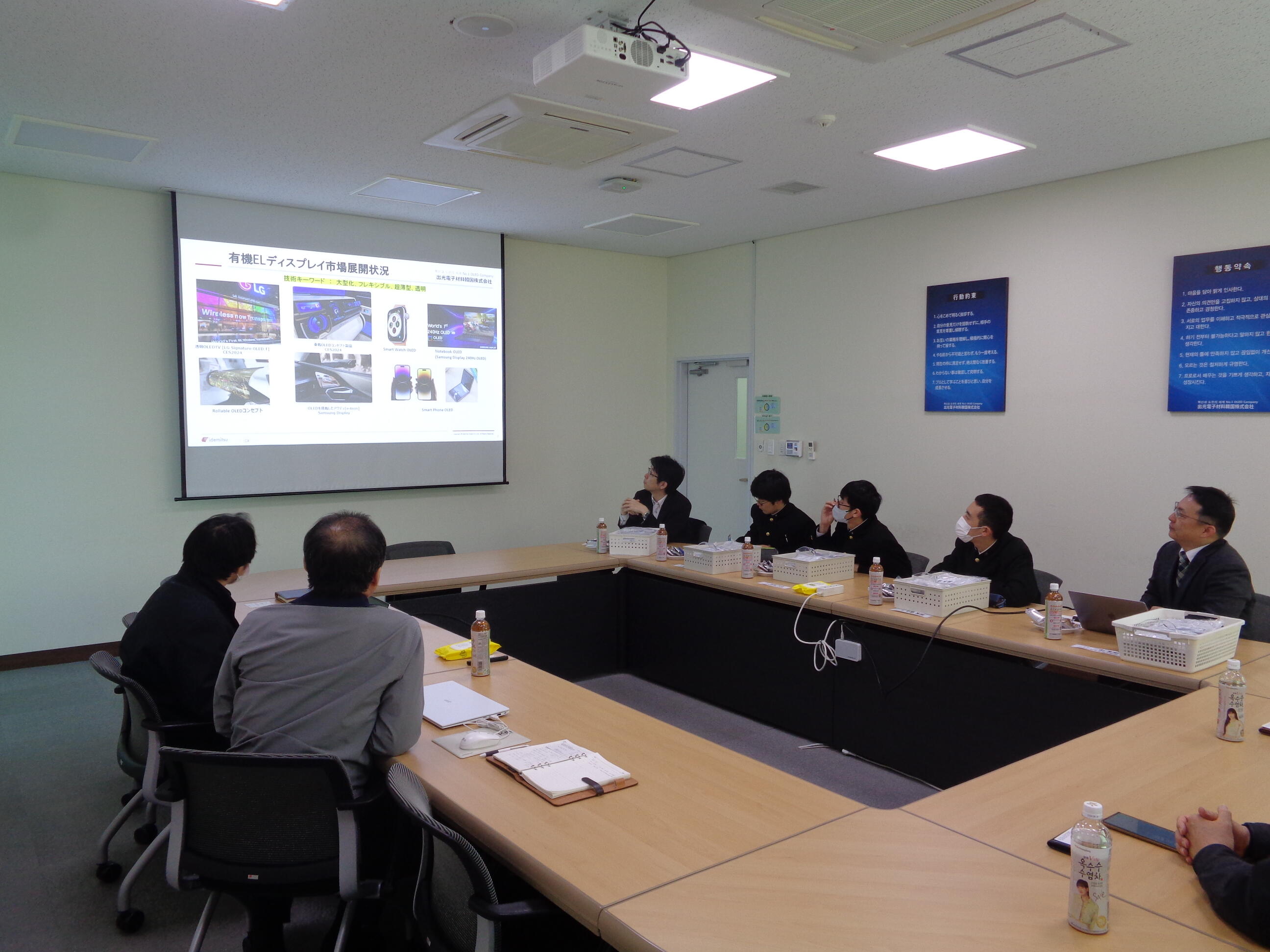韓国にて企業見学会を実施しました。
令和6年3月13日(水)から3月16日(土)の3泊4日で、韓国にて企業見学会を実施しました。参加者は電気情報工学科3年の学生3名及び引率教員1名でした。
3月13日(水)に宮崎空港から仁川空港へ移動し、実際の見学会は3月14日(木)から実施しました。
3月14日(木)はソウル南部の都市、城南(ソンナム)市にあるDISCO HI-TEC KOREA(DHK)を見学しました。現地社長の渡辺様によるご挨拶をいただいてから、アプリ部Managing Directorの松本様による会社(業務)説明、管理部General Managerの小松様によるDisco独特の経営手法(社内通貨や業務改善(PIM)活動))についての紹介がありました。その後、社内見学では、ダイシングソーやグラインダなどの装置や作業風景を見学し、さらにバックヤードの見学では、掲示物である優秀なPIM活動のスライド等もお見せいただき、幅広い業務を直接見学することができました。また、昼食会では、再度、渡辺社長様も含め懇談の機会を設けていただきました。
3月15日(金)はソウル北西部の都市、坡州(パジュ)市にある出光電子材料韓国を見学しました。日程調整をしていただいた出光興産人事部の荻野様もわざわざ日本からお越しいただき、我々と共に見学会に参加していただきました。現地社長の徳光様によるご挨拶をいただいてから、General Managerのパク様、Team Leaderのリー様等により、会社(業務)説明や有機EL素子の原理等の説明などのお話を聞くことができました。その後、クリーンルームに入り、材料の昇華精製設備等を見学させていただきました。
3月16日(土)は仁川空港から福岡空港を経由し、宮崎空港に戻りました。
参加した学生の感想
黒木遥斗さん
DHKでは、韓国で働いている日本人の方々や韓国人の方からの話を聞き、どういった形で仕事に取り組んでいるか、ディスコグループでの取り組みについて深く学びました。出光興産では、クリーンルームに入ったりと、主に企業の技術について知ることができました。どのように素子を作っているのかを見学したり、実際に素子を間近で見ることができました。企業の方との会食では、企業説明では話せなかったようなお互いの国の文化についてなどの話をすることができて、楽しい時間になりました。韓国で街中を歩いた時に日本との違いを見ることができたり、夕食の時間には日本とは少し違った雰囲気で食事をしたり海外と日本の違いをとても実感しました。日本と韓国の文化の違いについて、実際に触れて学ぶことができたのでとても身になった企業見学会だったと思います。
中村 南翔さん
二社の企業に行って、それぞれの良さと企業によっての雰囲気の違いを感じました。一つ目の企業ではユニークな会社の取り組みがあって、とても面白いと感じました。特に一枚の紙に書いて一分で発表するPIM活動については、わかりやすさの工夫などについては自分自身学べるところが多くありました。世界に展開して今を支える半導体の会社なので、学べる部分がとても多かったです。二つ目の企業では、有機発光ディスプレイ(OLED)材料を生産して、検証しているところを見学させてもらいました。習った知識が組み合わさってできてるような機械だったり、全く知らない知識を使っていたり、とてもわくわくした見学でした。個人的に気になっていた透明なディスプレイの仕組みについても少しお話を聞くことができてうれしかったです。働いている韓国人のほとんどの方が日本語を使うことができて、とても驚きました。両方の企業とも会食をしましたが、韓国と日本の違いをよく知るきっかけになりました。食事をする上でのマナーについても韓国は日本と違っていて、料理の付け合わせのようなものが数種類出てきて、おかわりも自由なのに無料で提供しており、驚きました。お店それぞれのおいしさがあり、それぞれの辛さがあリました。韓国はスーパーに行くと、日本より物価が高くて自炊してもお金がかかるなと感じました。特に卵は日本の2倍以上程値段が違っていたので驚きました。
前原 悠之介さん
一社目はDISCOさんを訪問しました。特に、PIM活動について興味を持ちました。この取り組みはかなり合理的なもので、会社内の情報が活発に飛び交うので、会社全体の成長につながることが多いなと感じました。また、Willマネジメントのように自主性を持たせるような制度もとてもいいものだなと感じました。二社目は出光電子材料韓国さんを訪問しました。有機ELについてあまり理解していませんでしたが、その説明は大変興味がわくようなものでした。研究機器に日本製品が使用されていたのがうれしかったです。この研修を通し学んだことは、疑問に思ったことはすぐに聞いた方がいいということです。相手はその道のプロなのだから見栄を張らずに聞いた方がよく、特に原理がわからない機器について質問した時などにそう感じました。この研修で得た経験を活かせるようにしたいと思います。