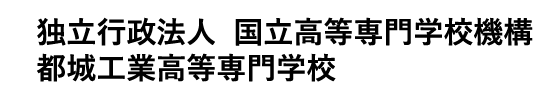教員・研究紹介
山下 敏明 教授

光反応による新規有機合成反応の開発および水素生産
当研究室では、クリーンエネルギーである「光」とマイクロサイズの「マイクロリアクター」を組み合わせ、これまでにない新しい有機合成方法の開発を行っている。また、再利用可能なバイオマスと光触媒を利用して、未来のエネルギーである「水素」を生産する技術を開発中である。
清山 史朗 教授

機能性高分子微粒子の調製とその応用に関する研究
マイクロカプセルとは直径がマイクロメートルオーダーの非常に小さな容器のことです.マイクロカプセルの中に入れる物質(芯物質)とマイクロカプセルを形作る物質(骨格物質)からなっています.骨格物質には合成高分子または生分解性プラスチック,芯物質にはタンパク質,塩類,その他用途に応じていろいろなものが使用可能です.応用例として,金属分離マイクロカプセル,抗菌マイクロカプセル,高吸水性マイクロカプセルなどが挙げられます.芯物質の内包特性やマイクロカプセル構造等に及ぼす様々な調製条件の影響を検討し,社会に役立つ材料の創製に取り組んでいます.
野口 大輔 教授

ナノテクノロジーで新素材を開発する
電子機器や光学機器に用いられる電子材料や光学材料、溶液中のイオンや分子の分離・選別などの機能を持つ膜材料、生体内での細胞との相互作用を制御した生体材料など、広く外場に対して物理的、化学的な応答を示す材料の作製と物性評価について研究しています。従来の合成方法の改良、レベルアップをはじめとして、新たな素材や新たな加工プロセスを検討しています。今までにない高い機能性を実現し、より付加価値を高めていくための技術の開発に取り組んでいます。
岩熊 美奈子 教授

貴金属や有価金属を効率よく回収できる分離剤の開発
貴金属は装飾品のほかにも携帯電話やコンピューターの回路、自動車などの工業製品に多く含まれています。それらの機器は寿命により廃棄されますが廃棄物の中には多くの貴金属や有価金属が含まれています。その量は鉱山1トンあたりの3倍から6倍の量含まれており、これらの中から貴金属を回収する技術は資源のない日本にとって重要な役割を持ちます。私たちの研究室では貴金属や有価金属を回収するために有機分子の分子設計を行い、効率よく回収できる吸着剤や抽出剤の合成をおこない、その分離機構について解明をしています。
高橋 利幸 教授
野口 太郎 教授

細胞骨格の分子ダイナミクスと機能との関係解明
我々の細胞には細胞骨格と呼ばれる繊維状タンパク質が存在します。これらのタンパク質は細胞運動、細胞分裂、筋収縮など様々な場面において中心的役割を果たします。このような細胞機能は癌細胞の浸潤や、細胞の増殖などに直接関わるものであり、我々にとって非常に重要です。私たちの研究室では細胞骨格に焦点を当て、これらの分子機構を分子生物学的、遺伝子工学的、生化学的方法論を活用して解明することを目的としています。
福留 功博 准教授
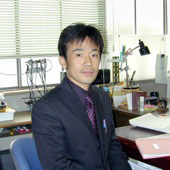
医療分野に応用される機能性高分子の合成と評価
高分子材料の分子設計は、医療分野においても使い捨ての材料から、生体内に長期間留置される生体親和性材料など付加価値のより高い材料まで鎬を削られています。当研究室では、ソフトコンタクトレンズに代表されるソフトマテリアルを中心に取扱い、その中で既存の刺激応答性モノマーと種々のモノマーとの共重合を試み、その共重合性と得られたソフトマテリアルの性質について評価しています。
岡部 勇二 准教授

天然物の新規有効利用法の検討
私の研究室では主に天然のオリゴ糖であるシクロデキストリン、製材所のチップやオガクズ等の木質副産物、魚の鱗のようなコラーゲンを含む水産加工残滓、南九州地方の土壌に多量に含まれるシラスなど、天然物について研究しています。これらの資源を有効に利用する方法を模索し、独創的な技術や付加価値の高い製品を開発することで地域社会に貢献することが目標です。
金澤 亮一 准教授
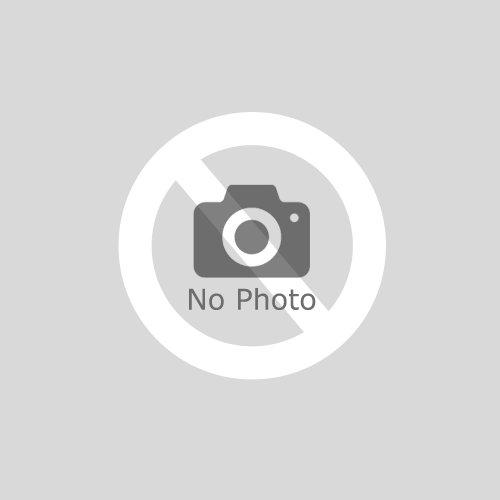
機能性高分子の工学プロセスへの応用
温度やpHなど周囲の環境変化に応答して大きさや状態が変化する機能性高分子を分離媒体などに利用し、省エネルギーなプロセスを構築することを目的に検討を進めている。
藤森 崇夫 准教授
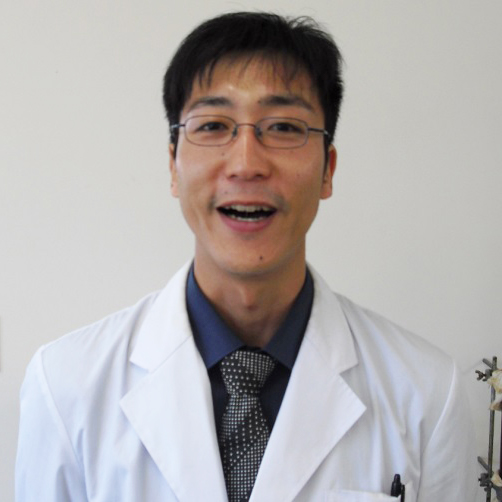
オキソ酸の化学的性質の解明と応用研究
オキソ酸として、ホウ酸やアルミニウム水和物を対象として現在研究しています。ポリオールはオキソ酸と錯体を形成する性質があります。ホウ酸と高い錯体形成能を持つポリオールについてその分子構造等から錯体の安定性を議論し、得られた化学的知見を応用してホウ酸の吸着剤開発を行っています。無機化学だけでなく、物理化学の知識や測定法を用いて研究しています。また、材料開発には有機化学の知識も用いています。
平沢 大樹 助教
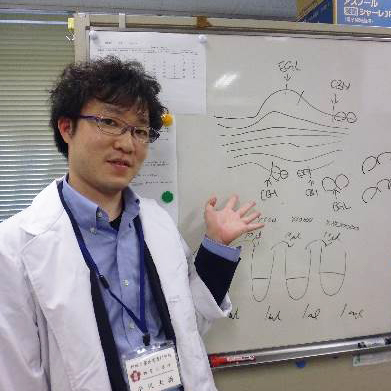
セルロース分解酵素生産菌の探索およびその応用
植物バイオマスの主要成分であるセルロースはでんぷんと同様に糖がつながった物質なので、分解することで糖が得られ様々な有価物質を作ることができます。稲わらや木などの非可食性バイオマスの利用は循環型社会の実現に必須な技術です。私たちの研究室では、セルロースを分解する酵素を生産できる微生物に注目し、セルロース分解微生物の探索やその特徴を研究しています。また、有用因子や酵素生産機構の知見を活かして微生物の育種も行います。
- 薗田 史恵 技術支援センター技術職員
- 丸田 映子 学生課教務係事務補佐員